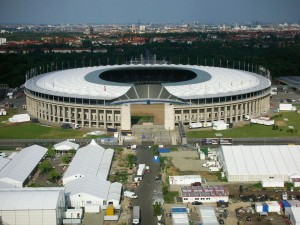※この記事は2006年2月に執筆されたものをJOA Review アーカイブ(第0号)に掲載しています。
移動日
2/8(水)
夕方、飛行機が遅れながらもトリノ空港着。今回はトリノ市内のホテル代があまりに高額なので、フォート・岸本さんの取材拠点にお世話になることにした。空港から岸本さんにTELしてタクシーでホテルに向かう。乗ったタクシーは英語が分からない運転手で困るが、ぶっ飛ばしてもらい何とかレジデンス・サッキに到着する。早速24時間警備のお巡りさん?に尋問され、パスポートを見せろと言われる。そこに丁度岸本さんのところの若い人に来てもらって助かる。車の音がしたので出てきてくれたのだ。この夜はピエモンテのワインをごちそうになり早めに休む。
2/9(木)
今朝は冬季オリンピック大会(OWG)のシンポジウム。朝、岸本さんに起こしてもらって草々 にトリノ大学へ向かう。マダーマ宮殿の近くのはずだが、場所がよく分からない。通行人に大学を聞いて行ってみると全く違うところに大学があるという。そちらのキャンパスに行ったがオリンピック・シンポジウムなど開催されていないという。また、マダーマ宮殿近くに戻って探してみる。あった、あった。古いバロック風の伝統ある建物だ。結局、遅れて会場に到着するが、また問題。建物の入り口には何もでていないのでよく分からないのだ。居合わせた学生に聞いてようやくホールの建物がわかる。会場に入ると丁度、開会の挨拶中。約50人強が歴史ある大学の建物の中に集まってシンポジウムが始まった。レジストレーションをすませて会場を見渡すとJanet Cahilがいて手を振っている。懐かしい顔だ。コーヒーブレークで久しぶりの挨拶を交わす。
にトリノ大学へ向かう。マダーマ宮殿の近くのはずだが、場所がよく分からない。通行人に大学を聞いて行ってみると全く違うところに大学があるという。そちらのキャンパスに行ったがオリンピック・シンポジウムなど開催されていないという。また、マダーマ宮殿近くに戻って探してみる。あった、あった。古いバロック風の伝統ある建物だ。結局、遅れて会場に到着するが、また問題。建物の入り口には何もでていないのでよく分からないのだ。居合わせた学生に聞いてようやくホールの建物がわかる。会場に入ると丁度、開会の挨拶中。約50人強が歴史ある大学の建物の中に集まってシンポジウムが始まった。レジストレーションをすませて会場を見渡すとJanet Cahilがいて手を振っている。懐かしい顔だ。コーヒーブレークで久しぶりの挨拶を交わす。
シンポジウムの開始は前IOCマーケティング部長のマイケル・ペインのキーノートスピーチから。「OWGのDNA」という興味深いテーマで話している。VTRを使うが、それはIOCのHPのCelebrity Humanityから見せている。あまりたいしたものではないが、やはり映像の力は大きい。OMERO(Olympics and Mega Events Research Observatory, University of Turin, Italy)というトリノ大学のオリンピック研究チームはトリノ大会による地域に活性効果やアルプス地域の再開発にテーマの照準を絞って報告していた。政治家や経済学者が中心の研究チームだからそうなるのだろう。
昼食からワインがそろえてある。ケイタリングを使って豪華な食事を楽しむことができるという配慮だ。午後は2会場に分かれて発表が続くが、テレビとコミュニケーションのセクションの方が人気だ。しかもカナダのCBCテレビが取材に入るので盛況である。私たちのセクションは歴史、文化、教育がテーマなので聴衆も少ない。しかし、歴史あるすばらしいホールでのシンポジウムだ。ドイツのマインツ大学のオリンピック研究チーム(このシンポジウムの共催チーム)のボスであるDr.ミューラーが病気で欠席したのが残念。代読でOWGの歴史研究の報告があった。英国の研究者であるガルシアとアンディにも会う。ガルシア女史とは本当に久しぶり。シドニー以来だ。彼女はオリンピックの文化プログラムについて報告したが、夏の大会の報告が多い。文化プログラムは規制がないので自由だが、様々なねらいがある多様性を持っている。
私はリレハンメルの冬季大会の終了後にこれまで3回実施されてきた「環境、平和、若者」へのメッセージリレーの現状について報告した。ほとんどの人が知らない世界の話題である。夏の大会はこの手のリレーをしていない。草の根の活動でヒーローやヒロインがいないためメディアの関心がないのが知られない大きな理由である。質問は、「夏の大会にはないのか? IOCは何故関与しないのか?」というものであった。夏は長野のチームが考えていること。IOCにはお金の関心しかないので、サポートはしないだろうというのが私の回答であった。
夕食のディナーはバスで1時間以上も走ったレストランへ。ピエモンテ州の郷土料理を堪能する。ドイツの友人でオリンピックの経済学者であるホグラー・プロウスとトリノ大学のチート・グアーラ教授にお礼の意味で法被を送る(JOAの佐藤さんにいつもお世話になっている法被だ)。これはハッピにかけてHappy Coatというのだと教えてあげる。デザインがコミカルで2人ともずいぶん喜んでくれた。記念写真もなかなかいい感じのものがとれた。メイルで送っておいた。遠くのレストランで夜遅くまで盛り上がった。実は、岸本レジデンスに帰ったのが夜中の1時半であった。帰り際にIOAのオリンピアの参加者でつくっているIOAPAという会合が翌々日の夕方にポルタ・ヌォーヴァ駅近くのホテルで開催されると聞くが、残念ながらその夜はフィギュアスケートのペアのショートプログラムのはず。残念。
2/10
今日は開会式。午前中にJapan HouseとMIZUNO caféを訪問する。水野社長は不参加とのこと。残念。その後、オリンピック・ストアに防寒コートを買い求めに行くがいいものはない(実は日本を発つ前にバタバタしてコートのフードを忘れてしまったので、今夜の開会式が寒いとたいへんだからと思って探しに行ったのである)。Asicsの製品ばかり並んでいる。オフィシャル・サプライヤーなのだ。いつもの定番の小物を買って昼は岸本弁当ですませてHolger Preusに会いに行く。彼をJapan HouseとMizuno Cafeに案内する。オリンピック経済学者らしい質問がJOCのスポンサーシップに向けられた。
その後、サン・カルロ広場でNBCのTVブースを見学に行くとトーチが3時過ぎにくるということ。それを見て開会式に向かうことにする。ドイツ研究グループと一緒に行動するが入場が遅くなる。セキュリティ・チェックはさほど厳しくはなさそうであるが、それでも長い列ができている。会場内に入ってもなかなか案内が分からない。イタリアらしいところ。ようやくたどり着いたBカテゴリーの席はフィールド内、傾斜がないのでよく見えない。最悪の場所だ。おそらくテレビ向けのパフォーマンスはCカテゴリーの方がよく見えたかもしれない。
雪と氷のない開会式。テーマはFireだ。
サプライズは、小野ヨーコ、パバロッティか。花火と警備のヘリの混在した開会式はソルトレークでもしかり。
閉幕後、フィールド内のBカテゴリーの観客はスタンドの観客が退席するまで待機させられる。おそらくシャトルバスには乗れないとあきらめ、徒歩で岸本レジデンスまで帰宅する。岸本さん達はバスで帰宅。私の徒歩の方が早く30分ほどでレジデンスに到着した。
後で岸本さんに聞くと、東京都の副知事や参事が見物にきていたそうで、パフォーマンスに感心しては歓声を上げていたそうである。この後この集団は一体何を調査するのか・・・。
大会第1日目
2/11(土)
トリノ市内。2/10の開会式も済み、翌11日には街はすっかりオリンピックムードになる。デコレーションも整ってきたようだ。今日は土曜日ということもあって子ども達の姿も多い。岸本さんと一緒に買い物がてら街の様子を見にでかける。先ずはガイドブックにも出ている有名なPayranoというチョコ屋さんに出かけてお土産を購入する。次ぎに、スポンサーズ・ビレッジに出かける。SAMSON、Panasonic、FIAT等の展示館である。公園のような一角にどーんとスポンサーがのさばっている。入場するにはセキュリティ・チェックを受けなくてはならない。おかしなものだが、、、。中にはゲーム機などもあり子供受けする企画も考えられている。レストランの一角にはローザンヌのオリンピック博物館のロゴで聖火やマスコットが展示してあった。もう少し大々的にオリンピック史や教育的な展示があっても良さそうなものであるが・・・。公園の中央には即席で氷が張られている。ロシアのブッチルスカヤがソロで氷上の舞を見せてくれたが、子ども達の滑りがあった方が遙かにいいものでは無かろうか・・・と思ったりする。
街中は結構な人出である。Italyartという文化プログラムにEthical Villegeというのがあったのでそこに岸本さんと出向く。近くのテレビ局の前で女性ボランティアに声をかけられて、岸本さんも一緒に「オリンピック休戦」の大きな本Bookに署名する。これは本当に思いがけずラッキーであった。Villageのテント内にはたいしたものはなかったが、オリンピックの理念と車いす式のそり(スレッジ)など身障者向けの展示がしてあった。このテントには人が少なく、やはり関心が薄いのであろう。
岸本さんと歩き疲れたのでpiazza Carlo Arbertoにステージとカフェがあったので一 休みだ。カプチーノを頼んでブラス音楽の演奏を聴く。ここでも子ども達の出番があればと、残念に思う。音楽を楽しんでいると変なベルの音がする。突然、悪魔のようなお面や服を着た「リセリ」と呼ばれる悪魔達が乱入してきた。あたりはカオス状況に陥る。どうも女性にとりついているようである。私も記念写真を1枚。世界的カメラマンの岸本さんにシャッターを押してもらう。これはいい記念になる。サン・カルロ広場で岸本さんと別れて一人でカナダハウスに向かう。広場では子どもと親であろうか、ミニホッケーに興じている。やはり、アイスホッケーを国技とするお国柄だ。ハウスはログハウスでできていて結構いい感じだ。入るとカナダのメイプルリーフのピン、小旗と新聞をくれた。中はすごい人出。やはり交流館はこうあって欲しいものだ。ゆっくりビデオ上映を見る暇はなく早々に立ち去る。
休みだ。カプチーノを頼んでブラス音楽の演奏を聴く。ここでも子ども達の出番があればと、残念に思う。音楽を楽しんでいると変なベルの音がする。突然、悪魔のようなお面や服を着た「リセリ」と呼ばれる悪魔達が乱入してきた。あたりはカオス状況に陥る。どうも女性にとりついているようである。私も記念写真を1枚。世界的カメラマンの岸本さんにシャッターを押してもらう。これはいい記念になる。サン・カルロ広場で岸本さんと別れて一人でカナダハウスに向かう。広場では子どもと親であろうか、ミニホッケーに興じている。やはり、アイスホッケーを国技とするお国柄だ。ハウスはログハウスでできていて結構いい感じだ。入るとカナダのメイプルリーフのピン、小旗と新聞をくれた。中はすごい人出。やはり交流館はこうあって欲しいものだ。ゆっくりビデオ上映を見る暇はなく早々に立ち去る。
夜はフィギュアスケートペアのSPを見に行く。初のフィギュア観戦。楽しみである。今回の標語はPassion Lives hereである。井上ペアの演技が楽しみである。中国ペアのできがすばらしい。しかし、少々細身すぎるのではと思うことしきりである。会場では何も盛り上げるものも子ども達のパフォーマンスもなくて残念。チケットはAカテゴリー(JTBがBカテゴリーを入手できなかったのでラッキー)。放送ブースのすぐ横。いい位置だ。斜め前には滑り終わったペアが得点発表を待つ席も見えるし、プレゼントの花束や人形を取りに行く豆スケーター達が待機しているのもよく見える。しかし、テレビカメラの数の多いことに驚く。TOBOのゼッケンを付けたスタッフが大勢見える。整氷の間にはやはり子ども達のアトラクションでも欲しいところだ。
大会第2日目
2/12(日)
日曜日の朝、買い物に出かけるがほとんど閉まっていて、果物もビールもワインも手に入らない。あきらめてパン屋が開いていたのでグリッシーニという細長いパンを買って帰る。朝食を簡単に済ませ、12時に街の様子を見に出かける。今日はメダル・プラザの向こう側、ガルバルディ通り、共和国広場、ドゥオーモあたりを狙って出かける。途中で、ポルタ・ノーヴァ駅の構内を抜けるとストアがあり、ビールも売っていたので早速買い込んでレジデンス岸本に届けておく。(ゲストなのであまり勝手はできないのであるが・・・。)
さて、街はすごい人出。さすがに日曜日。チョコレートの屋台街に出ると既にお土産を買ったPayranoが出店していたので、バラッティという三角チョコを買ってみる。10ユーロもするのできっと大変においしいのであろうと推測する。ドゥオーモへ行くとほとんど人がいない。流れはガルバルディ広場に向かっているようである。メダル・プラザで流れがせき止められているようである。観光気分になって教会の中に入ってみると、そこはキリストの亡骸を包んだといわれている聖骸布が置かれている教会であった。イタリアンアートという文化プログラムの1つである地下の教会といわれる博物館も見て回った。王宮には入れないということであった(実は入れることは帰国して知った。残念)。夕方のアイスホッケー女子の試合を見に行くためのシャトルバスを確認するが、トラムで行けというのでやはり、いつものポルタ・ノーヴァから行くことにする(実は同じトラムであることが後に判明。しっかり歩いたなー)。共和国広場という名前に惹かれて行ってみるが、どうも怪しげな人たちが沢山たむろしている。早々に立ち去り、ガルバルディ通りに向かう。多くの人出で大道芸もいる。帰国するときにバスでここを通った。バザールが沢山でていた。そのときは日曜日でバザールも休みだったのである。
街の散策の途中に、O.コスが提唱している”Right to Play”の展示館がありのぞいてみるが、誰もいない。昔はOlympic aidと呼んでいた世界中の子ども救済支援活動である。残念な限りである。写真とVTRを取ってまた散策を続ける。街中に子ども達のパフォーマンスなどがないのが残念である。このガルバルディ通りの途中にユーベントスのサッカーショップがあった。ここではお店をバックに記念撮影するサッカー好きの観光客の姿も見られた。お昼時、マダーマ宮殿前に行列ができているピザ屋があったのでマルゲリータを1枚買って立ち食いしてみるが、さほど感心するほどの味ではない。さっさとシャトルバスでアイスホッケーの会場に向かう。
エスピオジオーネというのがホッケー会場。磯崎新設計のホッケー会場とは別のもので ある。シャトルを降りると会場の反対側までぐるりと回される。結局ポー川沿いまで歩くことになり、ついでに川縁りの写真を撮影しておいた。入り口の周りには湖上の雰囲気の建物やすてきな池と滝が設置してある。しかし警備の警官が沢山いる。警備陣の彼らは一体どこに住んでいるのか心配になる。セキュリティ・チェックではミネラル・ウォーターのキャップを取られてしまう。全く、場所によって方針が違うようである。会場内でミネラルを買うとこれもセキュリティのためキャップをとられてしまう。どうしてセキュリティのためなのか、全く分からない。おかしなものだ。案の定、座席に座ると隣の子ども連れの母親がボトルをけっ飛ばして倒してしまったではないか。
ある。シャトルを降りると会場の反対側までぐるりと回される。結局ポー川沿いまで歩くことになり、ついでに川縁りの写真を撮影しておいた。入り口の周りには湖上の雰囲気の建物やすてきな池と滝が設置してある。しかし警備の警官が沢山いる。警備陣の彼らは一体どこに住んでいるのか心配になる。セキュリティ・チェックではミネラル・ウォーターのキャップを取られてしまう。全く、場所によって方針が違うようである。会場内でミネラルを買うとこれもセキュリティのためキャップをとられてしまう。どうしてセキュリティのためなのか、全く分からない。おかしなものだ。案の定、座席に座ると隣の子ども連れの母親がボトルをけっ飛ばして倒してしまったではないか。
ゲームには2424人の観衆が詰めかけたという場内放送が最後にあった。女子のホッケーがどのようなものか楽しみにする。しかし、ゲームはカナダの一方的な試合。12-0でカナダの圧勝。中でも驚いたのが試合を盛り上げようとする趣向だ。座席の通路にチアガール達が出てきて踊り出す。笛でゲームが止まれば拍手を求められ、チアガールが踊り出す。会場はゲーム内容よりもエンターテイメント志向がありありである。テレビ向けの志向が見え見えである。観客もそれをよく知っているようで、演じさせられながらもビデオ画面に映ることを楽しんでいるようだ。しかし、今回の会場では座席の前方にクレーンカメラがあり、見るのにじゃまになる。しかも端の方で、、、。少々残念。ロシアの子ども連れ、イタリアの子ども連れ、カナダの子ども連れと親子連れの光景がほほえましい。子ども達は館内の音楽に合わせてすぐに踊り出す。そのうちに、クレーンカメラが執拗にカナダ国旗を振る女の子達を狙っている。ディレクターの指示? カメラマンのアイデア? 子ども達にとって素晴らしい思い出になるに違いない。この会場でもグリッツとネーベというマスコットが人気であった。このマスコットが人気で売れ切れだそうだ。私はそんなに気に入らず、お土産には買わなかったのだが、、。氷上のトリノのロゴの向きから正面席中心、チアリーダーはバックスタンドで踊る。正面席はメディアがどーんと構えているし、その下は役員などであるから、どう見ても正面席から見たテレビ向けのショーアップとしか思えない構造である。
夜はサン・カルロ広場でメダル・セレモニーのパブリックビューイングである。寒いが膝掛けまで出してテレビウオッチする。音楽ショーの後3種目の表彰が執り行われた。会場内には整理券がないと入れない。広場に設けられた大型ビジョンで見ると、会場内は空席が結構目立つ。役員の席か?膝掛けを用意してあり大変なことである。子ども達がヒーローやヒロインにふれられるチャンスは? この夜は、男子スピードスケート5000mでイタリアの選手が銅メダルを取ったのでかなり盛り上がった。やはり大会が始まれば、地元も大いにわくようである。
夜は岸本さんにまたワインをごちそうになりながら、様々な話を伺い、IOC、JOCの問題を話し合う。オリンピックがおかしくなっていることや、JOAの活動などをいろいろ考えさせられた。
今日のまとめ:
* 街中に選手や観光客が大いに増えて楽しんでいる。
* 子ども達のパフォーマンスは見られない。
* 会場付近は警備ばかり目につく。盛り上げる気配がない。
* セキュリティは厳しいがミネラル・ウォーター栓の開封には困ったものである。
* 会場内はアナウンサーとチアリーダーによる盛り上げとテレビ志向の仕掛けである。
* パブリックビューイングはもう少し盛り上げ方があってもよいのかも・・・。
* 他の所でのパブリックビューイングは?
大会第3日目
2/13(月)
朝、岸本さんにおにぎりの朝食をいただく。おいしい朝食だ。その後、岸本さんと一緒に散策にでる。先ずはカナダハウスへ。先日と比べあまり人がいないのに驚く。平日のせいかも。カナダ政府のPRビデオであったのでやはりVANOCのプレゼンテーションが欲しいところで、残念に思う。この後、岸本さんの電話にチャージし、郵便局に絵はがきを落とすのにつきあう。残念ながら時間が無くなってきたので、エジプト博物館の見物をパスし、モーレ・アントネッリアーナというトリノのシンボルタワー内にある映画博物館を見に行くが、生憎月曜日は閉館日。全く残念。立ち食いピザ屋の「ラ・ピラミデ」でマルゲリータを食べると、やはりこれはおいしい。お勧めである。簡単な昼食後に岸本さんをヌオーボに案内し、少々時間がおしていたので急いでシャトルバスに乗ってオーヴァル・リンゴットに向かう。途中で停車駅を間違えて降車するが、そこはIOCの本部でMPCもあるところであった。そこから、オーバルまでかなり歩かなければならなかった。疲れているのにやれやれである。バスに同乗していたオランダのサポートと一緒に降りればよかったと悔やむ。セキュリティでは持ち込んだ水のキャップを開けさせられ、それが後のザック内水浸し事件となる。偉い目に遭う。
車中からオランダの応援団は面白い格好をしているし、オレンジカラーで統一している。それに、にぎやかだし、かなりの人数でもある、、。エンジ色のカナダの応援団もいるが、圧倒的にオランダのオレンジカラーだ。帽子に趣向を凝らしているものが多いようだ。オリンピックをお祭りのように楽しんでいる。これが一番大切なのだ。さすがにメダル希望種目の男子500スピード種目。日本人応援団も多いが、おとなしい。ともかく、面白そうな衣装や帽子をカメラに納めておく。座席はフォート岸本さんのチームの近く。最後のカーブの所だ。周りにはカナダの応援団もいる。しかし、圧倒的にオランダのオレンジカラーが席巻している。隣にはミラノからJTBのツアーで加藤丈治一家の応援団を率いてきた川村さんというガイドの方だった。23年もミラノに住んでいるとのこと。大変なものだ。
レースは日本人勢は惨敗。及川君が4位になる。加藤も清水も敗れてしまった。メダルしか関心がない日本人応援団には痛い結果であった。余り下馬評に挙がらなかったアメリカの選手が優勝をかっさらった。韓国も強かった。「この一枚」といういい写真を撮ろうとしたが、なかなかむつかしい。機材も大事だが、やはり経験不足だ。即席のカメラマンには高速スピードのアスリートの滑りなどデジカメで追いかけられるものではないのである。
このオーバルには外にステージが設けてあったので、何か盛り上げる催しものがあるのであろう。10組が滑った後で整氷する合間に、チアリーダーが場つなぎをする。こんな時には子ども達のパフォーマンスが欲しいところだ。セキュリティも面倒なのだろう。子どものパフォーマンスはオリンピックから消えてしまった。また、チアリーダーで盛り上げるのもいいが、その前に滑った選手とその後に滑る選手とではリラックスや集中力の上で支障があるのでは・・・。どちらに働くにせよ、選手には困ったことではないのか? 終了が7時半なので、都合4時間も館内にいるので、その間の盛り上げ方に工夫が必要であろう。
試合結果は残念であったが、レジデンス岸本に帰宅するとカメラマンの藤田さんが片付けにやってきて今日のスピードの結果を語ってくれる。やはり長いことアスリートをレンズを通してみているのであろう。「強い選手がやはり勝つ」という結論を聞いて納得する。日本のメディアは外国選手のことを伝えないが、カメラマン達はいつも見て知っているのだ。
2/14(火)
今日は帰国の日。朝は、体調が不良であったが何とか努めてジャパンハウスに向かう。遅塚選手団団長も来館中であったが接客中。帰国することをJOCの中森さんに告げ、水を1本もらって空港へのバスに乗り込む。途中渋滞するが早めに空港へ。ルートはいつもと違うようで、数少ない乗客達がバスの運転手と何か話している。ユーベントスのショップ前を通り、共和国広場前をバスが通る。バザーが沢山でていて、この前と違ってすごい人出だ。バスはまだ工事中の小さな空港につく。免税店でお土産にバローロの高級ワインとグリッシーニを買い込む。チーズは売り切れなど、品揃えは今ひとつ。小さなオリンピック・ストアもあったが、閑散としていた。アルバイトのお嬢さんはミラノ大学生。ボランティアは偉いがお金にならないので、バイトの方がいいと言っていた。お金を貯めてアメリカに留学したいのだそうだ。いろいろな若者がいるのだ。しかし、オリンピックボランティアはして欲しいと思う。帰りの全日空機では窓側の席、これも残念。疲れていて、ほとんど寝るであろうが、動きづらい。アルデベルチ、トリノ!!
Olympically, NAO